稲核風穴保存会
令和元年12月2日 : 「日本アルプス―登山と探検」の中の稲核風穴
Walter Weston ウォルターウェストン(1861‐1940)
ウォルターウェストンの本に稲核の地名と共に風穴についての記述がありました。
英国人宣教師として来日し、日本滞在は1888ー95年、1902ー05年、1911ー15年の三度に渡り、
日本滞在中、各地の山を登り日本アルプスの山々や当時の山村 の様子や人々の風俗・習慣などを
海外に紹介した日本登山史の中でも極めて重要な方です。
上高地には、日本山岳会により彼の偉業を称えてレリーフが建立されている。毎年6月にレリーフの
前で地元安曇の小学生らも参加して、記念山行やウェストン祭が行われている事から安曇地域では
有名な存在です。
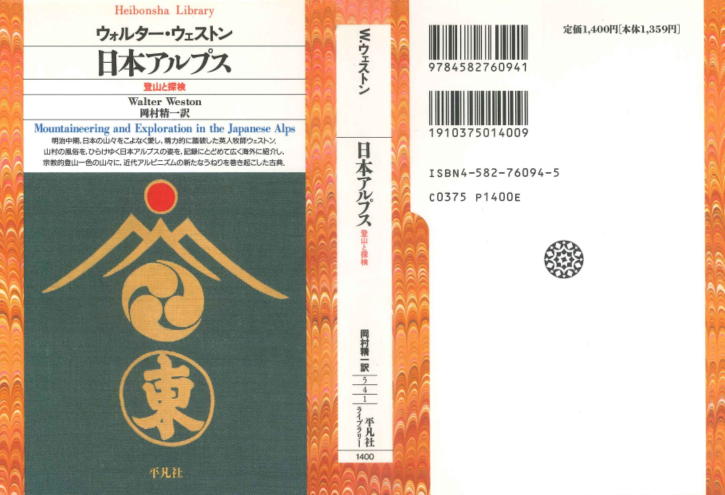
ウォルター・ウエストン 「日本アルプス 登山と探検」 ( 岡村精一訳 平凡社 )
時代は明治20年代初めから大正の初めまでの当時の人々の風俗が記録されており、興味深い記述
がみられます。例えば、当時の人々は雷鳥狩りをしていたとか、雷鳥の羽は蚕の卵を紙の上に集める
のに重宝して養蚕家に人気であるとか、また、白骨温泉に病気療養に人々が来ていることなど、また
橋場、大野川、徳本峠、などの身近な地名が度々出てきます。
読み進めると、身近な場所にウエストンの足跡があったと思われ、感慨深いものがあります。
稲核と風穴の事が登場する一節は、ウェストンが岐阜から安房峠を越えて白骨温泉に寄り、大野川を経
て前川渡に出た後です。
うねうねした谷間を曲がるごとに、新鮮な美しい景色が目をそばだたせた。前川と梓川の合流点近くに、
液状ガラスの広い一枚板のような奇妙な滝が梓川の左岸の黒い岩の光った面にかかっている。さらに
進むと、右側に一つの小さな滝がほとんど通路の上に落ちかかっている。そしてしぶきは青貝色の驟雨
となって、断崖の基部に開いている洞穴の口の前に飛び散っている。絵のような橋で、路は岸から岸へ
と渡るようになっていて、風景に変化を与えている。稲扱(イネコキ)では谷間が広くなってきて、気持ち
の良い開墾された渓谷に、人家が散在するようになる。ここの農夫たちは風穴(カザアナ)という、岩に穴
を切り込んで造った倉を使っている。その倉のなかに、冬の嵐を避けて、乏しい収穫を安全に蓄えられる
のである。 六時半にはこの狭い谷間はもう黄昏に包まれた。ゆらゆらする提灯の黄色い光が、私たちを
橋場へと案内してくれた。
(ウォルター・ウエストン 「日本アルプス 登山と探検」 岡村精一訳 P107より 抜粋)
現代の我々が失っている自然風景への感性を生々とした描写によりその美しさを思い起こさせるととも
に明治期の稲核の人々の生活に風穴が深く関わっていた記述が残されています。
清水先生と上高地温風穴探索へ
私たちも上高地の風穴へ
清水長正先生の上高地風穴探索
上高地の風穴
酔い好い列車
お酒の蔵出し
新酒の蔵入れ
Wウェストンの著書
荒船風穴見聞記
温風穴を探す
稲核地区
蚕種冷蔵風穴
航空写真
風穴画像
「水殿風穴」の温度
地区内風穴詳細表島立公民館見学
こども新聞
公民館長会見学
第2回定期総会
紹介パンフレット完成
パンフレットの取材
設立総会
設立理念